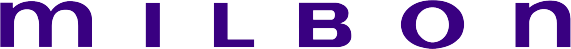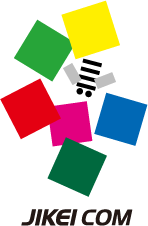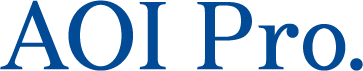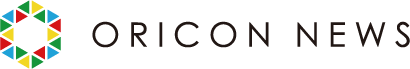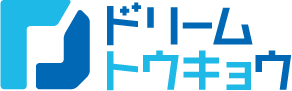【6/18 Thu 会場レポート】イッツコム @ 二子玉川
6/18 金曜日11:20からは二子玉川のイッツコムでインターナショナルプログラム 5、アジアインターナショナル&ジャパンプログラム 7、インターナショナルプログラム 6、アジアインターナショナル&ジャパンプログラム 9が上映されました。

本日、11:20からスタートとしたのはインターナショナルプログラム5。
作品上映後は『僕らの時間』のOrion Eshel 監督)とLuther Clayton 監督にオンラインで参加頂きました。
Q&Aの様子はYou Tubeでご覧いただけます。
https://www.youtube.com/watch?v=wCZS_pO0aGw
『僕らの時間』は兄弟のような二人の少年が、自然や音楽、言葉を通して世界の美しさを共に発見していく。しかし、学校での乱射事件により二人の運命は大きく変わってしまう…、というストーリー。
まず、Eshel監督とClayton監督がオンライン上で挨拶。二人とも10代後半にみえる若い監督です。Eshel監督はコスタリカからつながっており、Clayton監督はイギリスからつながってくれました。日本は午後1時ほどでしたが、イギリスでは午前5時とのことです。まず、この作品のきっかけを両監督に聞くとEshel監督は「我々の世代でなかなか学校の乱射事件の問題を話す機会がないのですが、重要な問題だと思っています。それでこの物語を作りました。で、最初は自分の書いたストーリーの英語チェックをオンライン上で出会ったLuther (Clayton監督)にお願いをしたのがきっかけでした」とコメント。Clayton監督も「そう、脚本の英語チェックをする傍ら、自分のアイデアも2,3ページ増やして戻したら、その後、共同の脚本作業となりました。」とコメント。
演技が素晴らしく、二人の友情の化学反応もばっちりだった主役二人については、オンライン上でオーディションをした際、一人の俳優から連絡があり、彼に主役の一人を決めた後、その彼の自分の友達を紹介してもらって、二人に出演してもらうことになった、ということでした。二人の主役は元から本当の友達だった、ということもわかりました。Eshel監督は、母国のコスタリカで、自分の半自伝的なストーリーを現在、執筆中ということで、いずれは長編映画化したい、と語ってくれました。Clayton監督は、現在、音楽のレコーディングに集中していますが、いずれEshel監督とまた、映画を作りたい、と話されました。
13:30からはアジアインターナショナル&ジャパンプログラム7が上映され、『吉祥寺ゴーゴー』の籔下雷太監督、そして、キャストの佐々木春香さんと小池樹里杏さんが来場しました。1970年からタイムスリップして現代の井の頭公園にやってきた若い女性ふたりと遭遇するひとりの老人の話で、出逢うはずのなかった彼らの運命がひとつに結ばれたとき、明らかになる結末が見どころです。

Q&Aの様子はYou Tubeでご覧いただけます。
https://www.youtube.com/watch?v=fMfc7HaSQuY
『吉祥寺ゴーゴー』の籔下監督は「昔の写真などをアーカイブされている吉祥寺今昔写真館委員会さんから、一枚の写真をテーマに作品を作る依頼がありました」とコメント。そこで、監督自らが脚本とプロデュースもされたそうです。初めて、台本を読んだ感想を問われて、キャストの佐々木春香さんは、「昭和といってもわからないので、昭和を勉強しなければ、と思いました。小池樹里杏さんは「監督からは、台本とDVDも頂いて、昭和の映画をみて世界感を感じて欲しい、とリクエストがあり、実際見てみると、しゃべりとか早いので、シャドウイング、衣装、メイクの雰囲気など勉強しました。」とコメントしました。
昭和風の衣装に関して、佐々木春香さんは「井之頭公園で、本番の時は恥ずかしかったです。結構目立ちました。」とコメント。小池樹里杏さんも「そう、(セリフで)自分のことも(あたい)とか言ってましたよね」と苦笑されました。
籔下監督は「衣装とお芝居しか表現できないので、昭和の喜劇映画みたいなのりをそのまま持ってきました。公園は現在なので、音楽とかもレトロ、ざらついた感とか出すようにしました。」とコメント。また「(制作)はシンプルで、舞台っぽくでいいと思いました。コロナ禍の隙間で日数もなかったので、一発勝負的な撮影でした。」とも話されました。
佐々木さんは、「私だけ蚊に刺されまくりました。水色のハイソックスはいているところだけ20カ所さされました。そういう意味では大変でした」と話されて笑いを誘いました。籔下監督は「エキストラのひと、街の人がマスクをしているので、それ自体、この作品が(ひとつの時代が切り取られる)アーカイブになると思います。」とコメントされました。
15:40からはインターナショナルプログラム6が上映され、『トランペット』の主役を演じられた曽根麻央さんが登壇されました。スイスのKevin Haefelin監督のコメディで、日本からニューヨークのジャズ文化を経験するためにやってきたトランペット奏者が、ブルックリンで迷子になり、地獄のような夜を経験する、という内容です。

Q&Aの様子はYou Tubeでご覧いただけます。
https://www.youtube.com/watch?v=DXIAy-CUpaI
曽根さんの自己紹介で、「作曲、トランペットの活動をしております。実は英語をしゃべれます。」と観客から笑いと拍手が聞こえました。今回、役者としては初挑戦ということで、映画制作の感想として「想像していたより、地味な作業の重ねでした。映画では2,3秒の歩くシーンも50メートルくらい歩くのを10回くらいやりました。その中からベストショットを監督が選ぶという作業ですね。音楽もそうですけど、ひとつひとつのピースを重ねる、という作業が音楽とも似ています。」とコメントされました。
作品は、2019年5月に撮影されたとのことで、その後、スイス人監督がフランスのスタジオでの作業を経て、2020年1月に録音を含めるポストプロダクションが行われたとのことでした。撮影場所、日数をきかれると曽根さんは「撮影はブルックリンです。何もないブルックリンを映すのは大変でした。撮影が5月で、真っ暗闇の時間が少なかったので、日数を重ねて撮影すると7日間かかりました。あと、(実景などの)サブショットを3日ほどありましたので、全体としては10日ほどの撮影でした。」とコメントされました。また、「ラストシーンには、即興演奏を1分くらいいれよう、という監督のKevinのアイデアでした。そして僕からの提案で、1,2テイクでやろう、ということになりました。カメラマンが朝のイメージを撮っている間、僕は目をつぶって即興をやっていて、後に人がいるというシーンがうまく表現できました」と話されました。
曽根麻央さんは、今後も都内を中心に活動されているとのことで、今後も彼のYouTube、オフィシャルホームページなどぜひ、チェックしてみてください。
最後、17:50からのアジアインターナショナル&ジャパンプログラム9が上映され、『誰のための日』の名村辰監督、そして、プロデューサー、脚本、出演の里内伽奈さん、同じのキャストの日高七海さん、また、『デジタルタトゥー』からは、呂翼東監督とプロデューサーの三川夏代さんが来場し、作品の経緯や脚本を読んだ時の印象、今後の撮影予定などのお話を伺いました。

Q&Aの様子はYou Tubeでご覧いただけます。
https://www.youtube.com/watch?v=zZcpfDykkR0
『誰のための日』は、ある姉妹が母親の三回忌の食事会のあと、お互いの生き方を理解できない姉妹の言い争いにヒートアップする内容です。
名村監督は、この作品が作られた経緯について話しました。「普段は俳優をやっていまして、去年の10月くらいに里内さんと同じワークショップに参加中、『監督をやってみたいんだよね』、と言ったら『じゃ、やる?』ということになり、映画を作ることになりました」とコメント。そこで、プロデューサー、脚本、そして姉を演じた里内さんは、「名村監督と物語については話をしましたが、私が脚本を書きました。私は一人っ子で姉妹がいないので、二人の喧嘩は空想です。大事にしたのは、家族同士の喧嘩において、一歩前、プラスになる言い争いの家族を作りたかった。」と話ました。妹を演じた日高さんは、私は姉ではなく、妹がいるので、言い合いはリアルでした。最後まで(お互いが)謝ることもないところもリアルでした」と語り、場内から笑いが聞こえました。名村監督は、「僕自身、(普段、おとなしい)妹にリモコン投げられたりしたことがあり、普段、人は、他人に見せない、兄弟(姉妹)で激高するシーンを撮ってみたかった」とコメント。
演技に関して、里内さんは、「もともと、日高さんとも過去に2,3回共演していたので、信頼している日高さんとならと思いました。過去に共演しても、言い争いのシーンがなかったので、今回、二人にとってもチャレンジでした。」とコメント。
日高さんは、名村監督の初監督作品だったので、とにかく監督に従おう、という気持ちでした。楽しかったです。」と話されました。初監督の印象を聞かれた名村監督は、「2日で撮った作品でした。宴会のシーンとリビングのシーン1日ずつ。時間もあまりなく、キャスト、スタッフがいる中で、なんとか完成しないといけない、という焦りの気持ちの印象です」と語られました。
そして、もう一組、『デジタルタトゥー』からは、呂翼東監督とプロデューサーの三川夏代さんが登壇されました。デジタルタトゥー』は近未来、憧れの企業から内定をもらっていた主人公が、父親が数年前にSNSに投稿した映像により就職できなくなるという、いまでもありえるし、未来にむけて非常に問題になりそうなテーマを扱っています。作品の経緯を問われた呂監督は、「プロデューサーの三川さんとはかつてデジタル広告代理店に勤めていた同僚でした。彼女はSNSのコンサルタントで、映画を作りたい、ということを聞いて、彼女の専門のデジタル分野をテーマにした作品を作りました。」と語りました。

三川さんは、「デジタルタトゥーでは、過去の投稿が未来に影響を及ぼします。今後、50年、100年後、(人の)過去の想いや気持ちの価値観が変わる中で、過去の発言の否定したこと、(例えば)当選した政治家の過去の投稿などが問題になる可能性は、一般の人々、誰にでも起こりうることなのです。これは、仕事をしていても感じました」と話されました。更に「何気ない投稿が未来では、何気なくないかもしれない。なので、今、それに気づくことも、気をつけることもできない。この映画では、父親の投稿のアカウントを削除するかどうか、迷うのですが、過去をバッシングされたとき、自分の過去を否定できるのか?」ということも問います。」と三川さんのコメント。
呂監督は、「30年後を想定した設定で、スマホはウェアラブルになっています。撮影日数は3日間、予備で1日。(CGなどのポストプロダクション)で1年5か月かかりました。」とコメント。最後のシーンについて聞かれた監督は、「はい、ロケットの音は、主人公が火星に言ったと思われる音です。最後の彼女の決断が、火星にいくということで、父親のアカウントが消された、ということです。」と話されました。
最後に、次のプロジェクトはどんな映画にしたいか問われると三川さんは、「次は、人間とロボットのお話をつくりたいです。」とコメントされました。
さて、二子玉川イッツコムでの開催は明後日6/20が最終日です!引き続き、作品の上映、監督などゲストによるトークイベント合わせてショートフィルムをぜひお楽しみください。